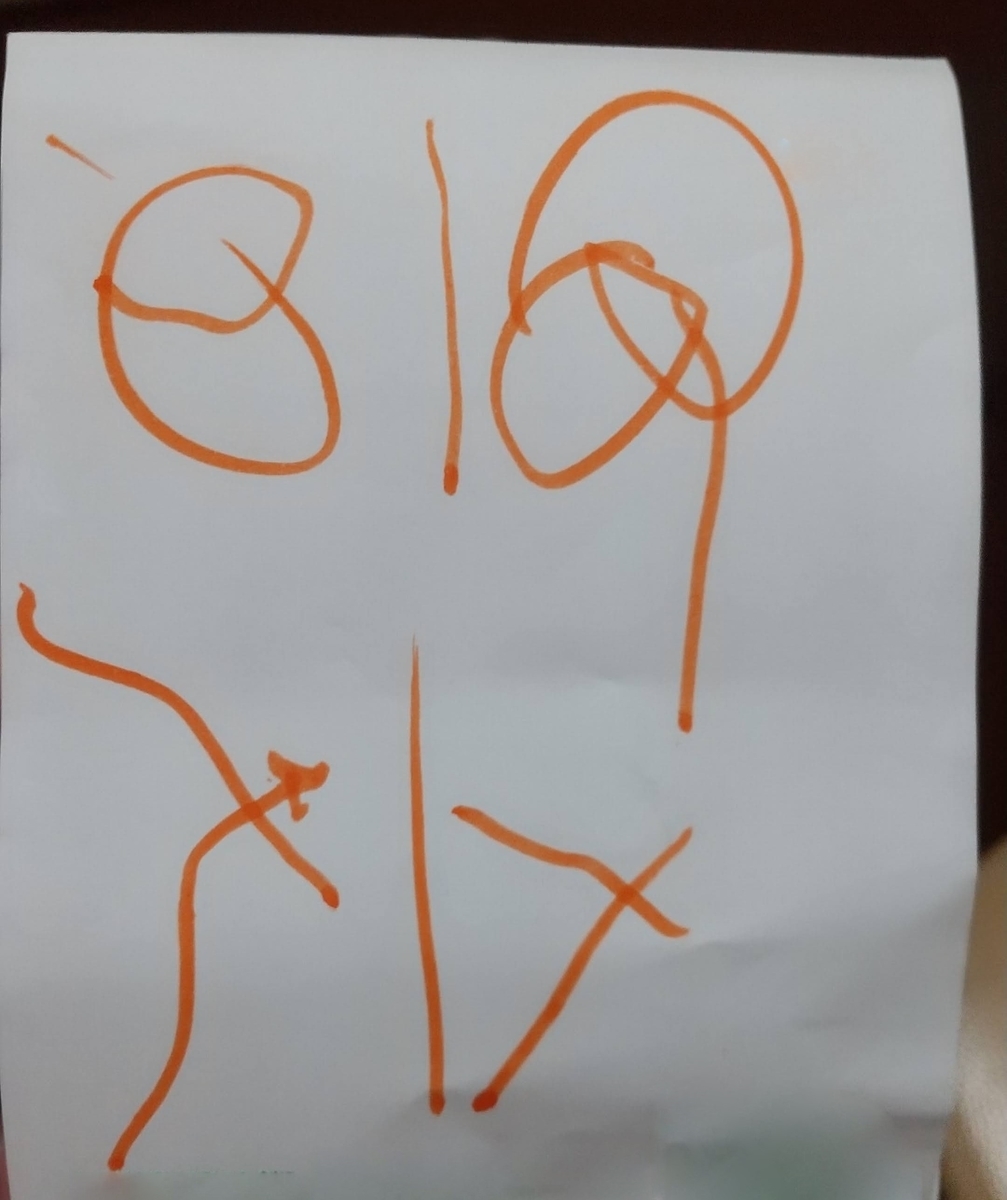東洋経済ONLINEにて、興味深い記事がありました。
toyokeizai.net
著者の石井氏によると、国語力は語彙をベースにして情緒力、想像力、論理的思考を駆使して生きる力とのことです。いわば社会という荒波を渡る「心の船」と表現しています。
我々夫婦としても、国語力は何よりもまず優先すべき内容だと考えています。
そして、今までそれに注力した3年間だったと感じています。
言葉の解像度
本記事では、『近年の子どもは、言葉で道を切り開くのが苦手。「ヤバイ」といった極端な表現でトラブルを生んだりする』と述べています。
この記事を読んで、最近の子どもは言葉の解像度が低いんだと感じました。
例えば、男女で色の認識は違うと言います。
女性の方が男性よりも、色を細かく認識すると言います。
(もちろん個人差はあり、男性でも色を細かく認識する人はいますが)
化粧品売り場に行くと、微妙な色の違いの口紅が沢山ありますが、女性はそれだけ細かい色を使い分けていると言えます。
これは女性は色の解像度が高く、男性は色の解像度が低いと言えます。
そして、女性はシチュエーションによって、その解像度の違う色を使い分けているということになります。
国語力の話に戻すと、通常は色んな事象に対して、様々な言葉を使用します。
嬉しい出来事と言っても、
・結婚、出産
・受験合格
・おいしい店を見つけた
・なくしたワイヤレスイヤホンが見つかった
などの各場面で使用する言葉は違うと思います。
そして、それら状況に対して言葉を使い分けることで、聞き手はより理解が深まります。
これは、言葉の解像度が高いため、聞き手にしっかり伝えたいことが伝わると言えます。
一方、色んな嬉しい状況に対して一律で「ヤバイ」と言うのは、言葉の解像度が低いため、理解を聞き手にゆだねてしまっています。
これが、著者の石井氏が述べているトラブルの原因と言えるのではないでしょうか。
国語力を身に付ける時期
国語力を付けるという意味では乳幼児期が適切と、私は考えています。
本記事では、本を読まない子やスマホで育つ子に対して警鐘を鳴らしています。
しかし、情報化社会が進み社会の在り方が変わっている昨今、子どもをスマホから遠ざけることは困難と言えます。
また、スマホは防犯に活用したりといった良い面もあるので、いずれ与えざるを得ないと思います。
しかし、乳幼児であれば、1人だけで外出することはありません。
また、「自分のスマホを持つ」といった考え自体持ちません。
親への依存度が高くスマホも持っていない乳幼児期は、国語力を身に付けるのにぴったりです。
そういった意味からも、先日記載した「大人扱い」するという話は効果的だと言えます。
(よろしければ、下記の記事もご覧ください)
rikeipapa.jp
子どもの自主性に任せる
本記事では、「目的ありきの遊びではなく、子どもたちが作り出した遊びが大切」と述べています。
私も完全に同意いたします。
よく「対象年齢〇歳」という記載がおもちゃにありますが、我が家ではあまりこれを気にしていません。
なんだったら、対象年齢が上のおもちゃをプレゼントしています。
※「部品を飲み込む危険がある」「塗料に有害物質が入っている」といった観点から対象年齢を決めている場合もありますので、そういった危険性がないことが前提です。
よく2人目は1人目よりも学習面で有利と言われます。
それは、1人目が遊んだり学んでいる姿を、生まれた時から横から学習できるからと言えます。
おもちゃの観点で言うと、2人目以降は出生時から上の子のおもちゃ(対象年齢が高いもの)が身の回りにあると言えます。
2人目以降の育児を経験した人なら分かるかと思いますが、2人目の子の周りから上の子のおもちゃを完全除去することは、時間的にも体力的にも部屋のスペース的にも不可能です。
また、日々忙しいので、上の子のおもちゃの使い方は、乳幼児任せになっているかと思います。
だとしたら、1人目に対しても、対象年齢に合致したものを与えなくてもいいのではないでしょうか。
対象年齢を決める際の具体的な方針というものはないそうです。
おもちゃ会社が「この遊び方だと対象年齢はこれぐらいかな?」と決めていたとしても、その遊び方をしなければいけない訳ではありません。
子どもが思いついた、大人からしたら想定外の遊び方はむしろ喜ばしいと言えます。
※再度注意書きいたしますが「部品を飲み込む危険がある」「塗料に有害物質が入っている」といった観点から対象年齢を決めている場合もありますので、そういった危険性がないことが前提です。
最後に
国語力は他者とのコミュニケーションツールだけではなく、学習ツールでもあります。
国語力がないことで、他者を傷つけてしまうといったことは避けたいです。
また、国語力がなく、学習に問題が発生するというのも由々しき事態です。
そのため、乳幼児期から大人と同じ会話レベルで接してあげて、国語力をどんどん身に付けるべきだと思います。
なお、石井氏の記事の最後の方に、「国は外国語など新しい教育を打ち出しているが、まずは国語力が必要」といった書かれています。
我々夫婦も、英語は学習の優先度は低いと考えています。
まずは日本語で色々学ぶべきと考えています。
この内容についても、いずれブログに書こうと思います。